- 梅の魅力
梅は果物?それとも野菜?意外と知らない植物学の話
更新日:
スーパーや青果店で見かける「梅」。見た目は果物のようですが、甘さが少ないので野菜に分類されるような気もします。
実際、梅干しや梅酒に加工して食べることが多く、生のままかじることはほとんどありませんよね。
この記事では、植物学や農業の定義をもとに、梅の正体を分かりやすく解説します。梅は果物か野菜か、どちらに分類されるのか、雑学感覚で楽しく学んでいきましょう。
結論から言うと梅は「果物」に分類される

結論として、梅は植物学でも農業でも「果物」として扱われます。「甘くないのに?」と感じる方も多いですが、分類の基準は甘さや用途ではありません。
植物学的な視点では「果実」として分類される
植物学の世界では、そもそも「果物」「野菜」という分類は存在しません。この分野で定義されるのは「果実」であり、これは花が咲いて受粉し、子房が成熟してできる部分のことを指します。
この基準で見ると、梅は春に花を咲かせ、初夏に種子を含む実をつける植物なので、植物学的には明確に果実をつける植物といえるでしょう。
また、植物学的な果実の定義は甘さや食べ方とは関係ありません。メロン・スイカ・トマト・アボカドのように、私たちが日常的に「野菜」と呼ぶものも、この定義ではすべて果実に含まれます。
農業や流通の世界でも「果樹(果物)」として扱われる
梅は、農林水産省の作物分類でも果樹作物に含まれ、青果市場でも果物として取り扱われます。
つまり、学問の分類だけでなく実際の出荷・販売の現場でも、梅は果物として扱われているのです。
梅が「野菜っぽい」と思われる理由
それでも、「梅ってなんとなく野菜っぽい」と感じる人が多いのは事実です。一番の理由は、生で食べることがほとんどなく、加工して使う前提の果実だからかもしれません。
梅は、梅干し・梅酒・梅シロップ・梅酢など、手を加えることで美味しさや香りが引き立つ食材。強い酸味や渋みを持ち、そのままでは食べられない点も一般的なフルーツのイメージから外れています。
こうした特徴の為、「果物よりも調理素材に近い」と捉えられやすく、野菜の仲間と混同されることがあるのでしょう。
「果物」と「野菜」の違いをもう少し詳しく

果物と野菜は、実は一つの基準で分けられているわけではありません。
植物学・農業・食文化など、見る立場によって分類が変わる為、「どっち?」と迷う食材が生まれるのです。
植物学・農業・食文化で分類が異なる
果物と野菜の分類は、次の3つの視点によって変わります。
| 視点 | 基準 | 梅の扱い |
| 植物学 |
「果物・野菜」という分類は存在せず、花が咲き受粉して実る果実として扱う |
果実をつける植物 |
| 農業・流通 | 数年以上育てる木本植物で、実を収穫するものを果樹として分類 | 果樹(=果物として扱う |
| 食文化 | 甘く生で食べやすいものを果実、料理素材のものは野菜のイメージ | 加工前提で独自の立ち位置 |
植物学では受粉して実るのがポイントで、梅は明らかに果物。農業の世界でも、梅は果樹園で栽培されて果実を食べるため「果樹(果物)」に分類されます。
しかし、食文化の視点になると少し複雑です。一般的に果物は甘く、生でそのまま食べられるものをイメージします。
その点、梅は酸っぱくて生食には向かず、加工してこそおいしくなる食材。そのため、果物なのに果物らしさが薄い独自の立ち位置になり、分類があいまいに感じられるのです。
どの基準を見るかで「果物のイメージ」が変わります。梅が「果物なのに野菜っぽい」と言われるのも、古くから調味料や保存食に使われ、食卓での用途が果物の枠を超えているからかもしれません。
スイカやイチゴは「野菜扱い」の果物
梅と同じように、「果物か野菜どっち?」と迷われやすい植物は他にもあります。代表的なのが、スイカ・メロン・イチゴです。
これらは、文部科学省の「日本食品標準成分表」では「果実類」と分類されています。甘くてデザート感覚で食べるものなので、果物のイメージをもつ方も多いでしょう。
しかし、農業の世界では、「野菜(果菜類・果実的野菜)」として扱われます。農林水産省の分類では「おおむね2年以上栽培する草本植物や木本植物で、その実を食用にするもの」を果樹としており、スイカ・メロン・イチゴは1年で育つ草本植物なので、野菜のカテゴリーに入るのです。
このように、植物学・農業・食文化の3つが混在することで、果物と野菜のどちらとも言える食材が生まれています。
参考:野菜の区分について教えてください。|農林水産省
梅の植物学的な特徴と分類

ここでは、梅という植物自体に注目してみましょう。仲間や果実構造からも、梅が果物であることが理解できます。
バラ科サクラ属という意外な仲間たち
梅はバラ科サクラ属に分類される落葉樹で、桃・杏(あんず)・桜・スモモなどと同じ仲間です。春先に可憐な花を咲かせる姿や、花の後に丸い実をつける姿は、桜や桃とよく似ています。
特に梅は開花時期が桜より早く、冬の終わりから春への移ろいを知らせてくれる存在です。控えめでありながら気品のある花姿や、ほのかに漂う香りは、桃や桜とはまた違った魅力があります。
果実の構造は「核果(かくか)」
梅の実は中心に固い種(核)があり、その周りを果肉が包む核果(かくか)という構造を持っています。このタイプの果実は、桃・スモモ・さくらんぼなどと共通し、果樹の中でも代表的な果実の形です。
核果は、種をしっかり守るための仕組みが発達しているのが特徴で、生命力の強さを象徴する構造ともいわれます。
この果実構造は、梅が植物学的に果物であることを裏付ける証。さらに、果肉が成熟すると独特の香りと酸味が生まれ、加工によって風味がより深まっていく点も核果の魅力です
梅は果物であり日本独自の食文化を持つ存在
梅は、植物学・農業のどちらの分類においても果物と言えるでしょう。バラ科サクラ属に属し、桃や杏と同じ仲間であることや、硬い種を持つ核果という構造も、果物としての特徴そのものです。
ただし、生のまま食べることがほとんどなく、強い酸味を加工によって活かす点から、一般的な甘い果物とは少し異なる独自の立ち位置を持っています。梅干し・梅酒・梅シロップなど、保存食や発酵食として古くから日本の暮らしに深く根づき、独自の食文化や健康文化を形作ってきました。
「梅は果物なの?」という素朴な疑問の背景には、分類の違いだけでなく、梅が日本で培ってきた豊かな歴史と文化が息づいているのです。
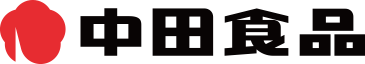






.jpg)

